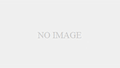アントニオ猪木の数ある名勝負の中でも2トップを挙げるとしたら、私は迷わずストロング小林戦とウィリー・ウィリアムス戦を選ぶ。
この2戦のうちでも、とくに格闘技色が強いウィリー戦には、果たして真剣勝負だったのか、それともエンターテイメントだったのか、という議論がある。なかにはブック(筋書きのある勝負という意味)などという声もあるが、実際のところどうなのだろう?
リアルタイムでこの試合を堪能した、古いプロレスファンである私の印象を述べてみよう。
アントニオ猪木vsウィリー・ウィリアムスとは
この一戦は1980年2月27日、東京蔵前国技館で行われた。
当時19歳だった私は真剣勝負の醍醐味に酔いしれたものである。ただ久しぶりにこの一戦を映像で振り返ってみると、あくまで私見ということでご容赦願いたいが、真剣勝負ではなかったように見受けられる。その理由は以下のとおりだ。
1.アリ戦よりもアグレッシブだった猪木
わずか4ラウンドで終わってしまったこの一戦であるが、猪木の動きを全ラウンド通して俯瞰すると、アリ戦に比べてはるかにアグレッシブだったことがわかる。
アリ戦を経験して真剣勝負に対する自信もあったのだろうが、実にいきいきと戦っていた。決してアリよりもウィリーの打撃が優れていると言うわけではないが、ウィリーにはパンチだけでなく、あの長い足から繰り出すキックもある。
普通に考えれば、とくに、1ラウンドあたりはアリ戦以上に慎重になってもおかしくないはずだ。
2.空を切るウィリーのハイキック
一番避けたい決着の一つに猪木が派手な打撃で倒されることがあったと思う。
時代が前後するが、永田裕志vsミルコ・クロコップ戦(ミルコのハイキック一発で永田がKO負け)のような決着だけは絶対に避けたかったはずだ。
プロレスラーは顔面以外の部位に関しては比較的打たれ強いが、顔面に関しては特別に強靭なわけでもない。
さて、この対戦では全ラウンドを通して、ウィリーの顔面を狙ったパンチやハイキックはほとんどクリーンヒットしていない。とくに、1、2ラウンドは顔面パンチやハイキックの空振りが多かったし、コントロールされたようなキックも散見した。
その反面、顔面以外の攻撃は比較的ハードヒットしていたように思う。組んでからのヒザ蹴り、背中に打ち下ろすヒジ、さらにはローキックが、時としてえげつないほどの威力で猪木の身体を強襲していた。
3.見事なまでに痛み分け
この一戦は、リング上に比べてあからさまに強弱の差がつき難い、いわばグレーゾーンともいえる場外で決着した。
しかも、2ラウンドと4ラウンドに、2人ともまるで吸い寄せられるかのように場外に落ち、カウントアウトのゴングを聞いているが、最初の場外はウィリーがマウントパンチで優勢に攻めているところ両者リングアウトの裁定。次は猪木が腕ひしぎを極めで優勢に攻めているところ再び両者リングアウトの裁定であった。
最終的には両者ドクターストップの裁定で決着したが、猪木は肋骨骨折、ウィリーは右腕の腱負傷と、こちらも見事なまでに痛み分け。圧倒的な優劣はつかなかった。

一触即発ながら守られた両陣営の看板
それにしても両陣営ともになぜあれほどまでに殺気立っていたのかとの疑問が残るかも知れない。
ただ、ホームリングだったこともあるが、新日本プロレスのセコンド陣は比較的冷静にふるまっていたように思う。一方、極真会館のセコンド陣は、必ずしも全員ではないが決着が決まっていることを伝え聞いていなかったのではないだろうか。また、もし伝え聞いていたとしても、アウェイのリングゆえに疑心暗鬼に陥り、常に極度の緊張状態にあったのではないかと思っている。
最終的に、選手のみならず両陣営の一触即発の挙動がこの一戦を一層盛り上げてくれたのであるが。
見事なまでに予定調和したこの一戦であるが、結果として新日本プロレス、極真会館、どちらの看板も傷つけることはなかった。当時すでに格闘技界の一大勢力になっていた両団体であるが、この一戦をきっかけに、その存在感をゆるぎないものにしたように思う。
最後になりますが、先月、ウィリー・ウィリアムス氏が天に召されました。極真会館に、圧倒的な強さだけでなく、超一流プロレスラーと対峙しても決して色褪せることがない華も合わせ持つファイターがいたこと、一生涯忘れません。心よりご冥福をお祈り申し上げます。