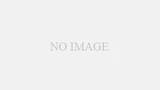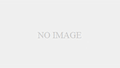小学6年生から中学1年まで少林寺拳法を習っていました。
私が通っていた道院では夏に合宿をします。当時の教室は子供部門と大人部門に分かれており、稽古を行う場所も異なっていました。
大人部門と一緒に稽古する機会はこの合宿と冬に行われる稽古収めの時だけです。今回は合宿についてお話させていただきます。
少林寺拳法で合宿をした思い出
この合宿では、市内にある山奥の公民館をお借りして行っていました。集合場所は子供部門で稽古をしている小学校体育館前です。集合したらハイエースなどの車でその公民館に向かいます。
日数は1泊2日で食事は先生を含め自分達で調理します。いつも日持ちがするカレーを作り、甘口と中辛に分けて作りました。
昼は近くの川で遊びながら、水泳、体力、筋力強化の訓練。夜はバーベキューで夕食を食べた後、キャンプファイヤーに肝試し、それが終えると先生の法話が始まります。
少林寺拳法の作務と脚下照顧とは
大人部門の人達は子供たちが寝る準備をしている間に、その日の反省会を行います。次の日なると皆起床し、基本稽古を外でやります。
この後全員で作務(さむ)と脚下照顧(きゃっかしょうこ)を行います。
この作務というのは掃除で、脚下照顧は玄関の掃除と靴をだらしなく脱ぐのではなくきれいにそろえて脱ぐことです。
これらが終わると先生の車に乗り、集合場所であった小学校に戻ります。これが合宿の流れとなります。
子供も大人も学べる合宿
先生はこの合宿に対して、私達に様々なことを学ばせる考えがありました。基本的に先生は稽古の際にはアドバイスや話を良くしますが、合宿中にはしません。
もちろん私達の行動にも干渉しません。自分達で考えて行動するようにしているのです。
例えば、キャンプファイヤーなどの薪を集めたりする際に、大人ではなく子供たちに行わせます。なぜなら、どのような木が燃えやすいのか、またどのような大きさがよいのかなど自然に触れ合うことによって学ばせ、考える力を持たせます。
また大人部門には責任感を持たせ、「誰が子供たちを見るのか」や「どうすれば効率よく出来るか」など運営を任せることによって、社会人で必要な「自分で考えて行動する」や「コミュニケーション能力を身につけさせる」など社会に必要な知識を学ばせました。
夕食の火付け係になった話
合宿に対しての思い出は小学6年生の時です。先生が炭に火をつけるのに時間がかかっていたので、「私がやります」というと先生は最初反対していましたが、渋々私にやらせてくれました。
私は夕食ができるまで遊んでいた小さい子供たちに、「乾いている木の葉や小さな枝を集めて」とお願いしました。当時人数が多くいたためすぐに集まりました。
火おこしのやり方ですが、最初にバーベキューセットの中に木の葉、小枝を入れます。火が大きくなるのを待ったら、中くらい木と炭を入れることで火が安定します。後は定期的に木や炭を入れ火力を調整するだけになります。
これを見ていた先生は驚いた顔をしていました。キャンプファイヤーを終えた後先生に「どうして火の扱いが上手いの?」と聞かれたので、私は「叔父さんに鍛えられました」と答えました。
叔父の友達に別荘を持っている方がおり、そこでよく薪をしていました。小さいころからそのやり方を教わりながら、やっていたので火を上手くつけられたのです。翌年の合宿では火つけの係に任命されたことを覚えています。
自他共楽の教えとリーダーシップ
この合宿では様々なことを学びました。「コミュニケーション能力を身につける」「自分で考えて行動する」こともですが、なにより「リーダーシップ」を学べました。
「リーダーシップ」というのは自分や他人のことを考えながら目標を達成する力だと考えています。それは少林寺拳法における「自他共楽」の教えに近しいものだと思います。
これから先様々な困難があるかもしれません。しかし「リーダーシップ」を身に着けられれば、困難に立ち向かえます。様々なことにチャレンジし、たとえ失敗してもそれはいずれ糧になります。
少林寺拳法の合宿を通じてこのことを学びました。
(文・ニコ)