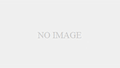武道には体格差をくつがえす技術があります。
また、実践を想定した武道的観点からは問題のある動きでも、スポーツ競技では有効というものもあります。
40代の現在も鍛錬を続け、背負い投げを得意技とする柔道家に、自分に合った技の発見から練習方法まで語っていただきます。
* * *
昭和最後の年、大学生になりました。
高校時代に続いて、大学でも柔道部に入部。きわめて弱小の大学でした。
それでも以後の年月を柔道にかけると決意し、まずは4年間で柔道部を出来る限り盛り上げ、自分自身は卒業後も実業団に進めるよう、稽古を重ねてきました。
1冊の柔道技術書に得意技のヒントが
170センチ・85キロと決して大柄ではなかったのですが、大学の中では体格の良い方でしたので、いつも団体戦では大将を務めていました。
当時の学生柔道では、団体戦は全て無差別級。多くの場合、自分より大きな相手と闘うこととなります。
そんな状況から、得意技にしようと練習したのが背負い投げです。いわゆる「担ぎ技」、小さい人間が巨漢を投げる「柔よく剛を制す」の理想を実現しやすいと言われる技です。
ひとくちに「背負い投げ」といっても、そのスタイルは千差万別。
そのころ日の出の勢いにあった古賀稔彦選手の背負い投げは、立ったまま相手を担ぎ上げ、豪快に叩きつけるものでした。多くの人が古賀選手の背負い投げに憧れ、同じような技を修得せんとしたものです。
しかし自分自身は決定的にスピードがなく、そのような背負い投げを用いることは叶いませんでした。
悩みを解決してくれたのは一冊の技術書でした。
その本は「バイタル柔道」と言います。
バイタル柔道に書かれていた背負い投げ
バイタル柔道は東京オリンピック中量級の金メダリスト・岡野功先生によるベストセラー。
全柔道家のバイブルと言われ、岡野先生の技術だけでなく、当時の名手たちの技術が網羅されている現在も色あせることのない名著です。
岡野先生自身も得意の背負い投げは立ったまま投げるスタイルでしたが、「バイタル柔道」には世界選手権四連覇の藤猪省太選手はじめ何名かの選手による低い背負い投げが解説されていました。
低い背負い投げは、ほとんどの場合に膝をついて仕掛けることになります。
ところが、昔から現在にいたるまで、背負い投げで膝をつくことは間違いとされ、正面きって指導されることはありません。
しかし、現実には多くの選手たちが膝をついた背負い投げで勝利を収めています。むしろ膝をつく背負い投げが一般化したために、反対に、古賀稔彦選手の「立ち背負い」が賞賛されたとも言えるわけです。
膝つき背負いが否定される理由を考察
さて、自分のようにスピードのない選手には、低く膝をつく背負い投げは適切な選択でした。
立ったまま背負い投げを施す場合、前回りの体さばきで180度振り返る動作を行います。これは2挙動となるため、非常なスピードが求められるものです。動作が遅ければ、相手も対処しやすくなってしまいます。
それに対して「膝つき背負い」は1挙動で飛び込み、反対向きに正座するイメージ。
動きがシンプルでコンパクトなので、スピードの無さをカバー出来る動作となっています。
そんな「膝つき背負い」ですが、なぜ歴史の中で継続的に否定されてきたのでしょうか。
基本的に柔道の技には、連絡変化が求められます。
「立ち背負い」ならば、防がれても小内刈りなどへの変化が考えられます。
「膝つき背負い」に問題があるとすれば、仮に投げることが出来なかった場合に変化がないこと。
そのまま寝技に入れば「亀」という防御姿勢を強いられてしまいますが、現代の競技ルールならば、寝技での不利な状況からも「待て」によって、再び立ち技から再開できます。
武道的発想から否定されたと思われる「膝つき背負い」。スポーツ競技の中では、十分に効果を発揮しうるものだと言えます。
膝つき背負いをマスターするコツ
この「膝つき背負い」で相手の股に入れば、全く力を使わずに相手を背中の上で回すように投げることが出来ます。
自分の場合、大学最後の試合で60キロ近く重い選手を投げ、勝つことが出来ました。
重量級の対戦相手は自分より背の高いことが多くなります。そのため低い位置に潜り込むのはそう難しくはありません。しかし、最初からそのような体格差を想定して練習していると、技術が向上しません。
自分の場合は、同じくらいか、少し背の低い相手と練習し、より低く入る練習を繰り返しました。
その結果、試合で自分よりも体格で上回る相手と対戦したとき、練習より楽に技がかかったのです。
試合でかける際のコツですが、膝つき背負いは変化こそきかないものの、他の技から連絡させることは実に効果的です。
具体的には大内刈り・小内刈りを用いて、相手の両足を並べてしまうこと。そうすれば、股の間に入ることが容易となります。
「膝つき背負い」は、しっかりマスターすればスピードのない人間でも、それを補って技を決めることができるテクニックです。
かからなかった場合に備え、最低限の寝技の技量も磨いておくことも忘れずに。
(文・大星タカヤ)